5、世界一の大都市?

幕府が江戸に開かれた当初、江戸には15万人ほどしかいませんでした。
同じころ、大阪には20万人、京都には30から40万人の人が暮らしていました。
1635年から参勤交代が始まると、江戸には大名屋敷が立ち並び、それに伴い人口も大きく増加していきました。
1721年に江戸幕府が人口調査を行なっていますが、その時の江戸の人口は約50万人でした。
しかし、この中には武家や寺社の人数が含まれていないため、それらを考慮すると約100万人という人口がいたことになります。
同じ頃のロンドンの人口は約85万人、パリでは50万人ほどでしたので江戸は世界一の大都市だったと言っても過言ではありません。
4、江戸時代の銭湯

1591年、江戸に最初の銭湯ができました。
当初は男女混浴で、現代のように湯船に浸かるものではなく、蒸し風呂タイプのものでした。
次第に風呂にお湯をはり入浴するようになりますが、それでも混浴であることに変わりはありませんでした。
ただし素っ裸というわけではなく、下着をつけて入るのが正しいルールでした。
しかし、下着で湯船に入るとお湯が汚れてしまうため次第に男女共に素っ裸で入るようになったそうです。
男女が裸で同じ空間にいるのですから、いかがわしい事故も起きたでしょう。
そのような風紀の乱れを抑えるため1791年には混浴は禁止となってしまいました。
もし、風紀を乱すような輩がいなかったら未だに混浴が当たり前だったかもしれませんね。
3、江戸のワイルドすぎる火消し

江戸時代の建物は全て木造で、壁は紙と泥を塗りこんだものだったので火にはとても弱い作りでした。
さらに100万人もの人たちが、長屋に密集して暮らしていました。
そのような町の中で一軒から火が出れば、一気に燃え広がり大火(たいか)になることは必至です。
そこで「江戸の火消し」が活躍するのです。
現代と違い、水の補給がままならない時代、火消しは火を消すことよりも、延焼を防ぐことを優先して行いました。
具体的には、まだ燃えていない家を壊すという方法です。
延焼を食い止めることにより大火にならないようにするしか打つ手がなかったのです。
もちろん水も使われていたそうですが、ボヤ程度しか消せませんでした。
なので、火を消すというよりは壊し屋みたいなものだったようです。
2、江戸っ子の頭脳

江戸時代、多くの子供達は寺子屋と呼ばれる学校に通い、読み書きやそろばんなどを習っていました。
武家の子供は勿論のこと、一般庶民の子供達も勉学に励んでいました。
これにより幕末の頃の日本人の識字率は7~9割にも及んでいたそうです。
同じ頃の海外をみてみるとイギリスでも2割程度、フランスにおいてはほとんどの人が勉強をしていなかったそうです。
このころすでに日本人の勤勉さが強く根付き、戦後の高度成長期にまで発展したのでしょう。
1、江戸時代の医者

江戸時代にも医者という職業は存在していました。
当時から世間的な地位も高く、武士しか乗れなかった籠にも乗ることができたといいます。
これだけの地位がある医者という職業ですが、医者になるための免許や資格は一切なく、誰でもなることができたのです。
そのため、当時の江戸には2500人以上、医者がいたそうです。
資格がいらない以上、ヤブ医者も多かったのだろうというのは想像に難(かた)くないですね。
もちろん、しっかりと研究していた人が多くいたからこそ、日本の医療もここまで進歩したのでしょうけどね。







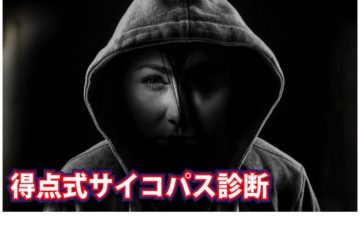

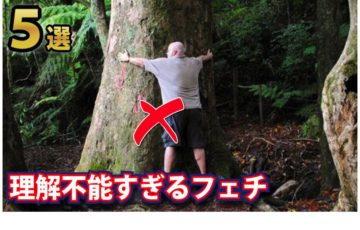
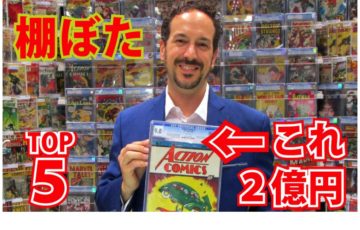

最近のコメント