4、かごめかごめ
歌詞の中に「夜明けの晩」とか「後ろの正面」という奇妙なフレーズがあるだけでなく、
歌詞全体の意味も分かりにくいため、『かごめかごめ』に得体の知れない不気味さを感じる人は少なくありません。
そのため、この歌を理解しようと、いろいろな解釈が試みられてきました。
その中でもよく知られているのが、妊婦が滑って転び流産したという歌だと解釈するものです。
「かごめ」は籠を抱いた女性、つまり妊婦を意味し、「かごの中の鳥」はお腹の中の子供だという説です。
「いついつ出やる」という部分「いつ赤ちゃんが出てくるか」という意味で、
「鶴と亀がすべった」は妊婦が突き飛ばされ、流産させられたという意味になります。
最後の「後ろの正面だあれ」は、誰が妊婦を突き飛ばしたのか、と問いかけているのです。
他にも、いくつか説がありますが、この流産説が一番多く語られています。
3、はないちもんめ
子供の遊び『はないちもんめ』は地域によって歌詞が少し異なりますが、遊び方はだいたい同じです。
ふた組に別れて、お互いに相手側のメンバーを自陣に連れてこようとする遊びです。
このうたの歌詞を素直に受け取れば、歌われているのは花の売買で値段交渉をしている様子ととれます。
「もんめ」は重さの単位であると同時に、江戸時代の貨幣の単位でもあったからです。
「勝って嬉しい」は「良い取引ができた」という意味と解釈することができます。
しかし、この歌に隠された怖い意味というのは、売買の対象は花ではなく子供だというものです。
日本では経済的な事情で子供を手放さざるをえない家庭が、裕福な商家などに子供を労働力として売り払う人身売買が行われていました。
この歌は子供を必要としている人買いと子供の親が値段の交渉をしている様子を模したものという意味が隠されているといいます。
事実、その方が遊び方にも合致しているといえます。
2、あんたがたどこさ
『あんたがたどこさ』は歌詞に「熊本さ」と出てくるので熊本が発祥かと思われがちですが、幕末、明治初期の関東地方で作られたものです。
江戸幕府と明治政府軍が戦った戊辰戦争時に、肥後の兵隊が埼玉県の川越市に来たときの様子を歌っているのだそうです。
子供たちが兵隊に「あなたたちはどこから来たの?」と尋ね兵隊が「肥後、熊本さ」と答えています。
さらに子供が「熊本のどこ?」と尋ね、兵隊が「仙波からだ」と答えます。
そこで子供が「仙波山にはタヌキがいるんだ、そいつを煮て焼いて食って隠す」と言います。
これには、裏の意味があります。仙波山には徳川家康を祀る神社、仙波東照宮があり、
「せんばやまのたぬき」は「たぬき親父」こと徳川家康のことです。
つまり、明治政府軍が倒幕することを暗に意味しているという歌なのだと言われています。
1、しゃぼん玉
童謡『しゃぼん玉』の歌詞を作ったのは詩人・野口雨情という人物です。
この歌の2番は「しゃぼん玉消えた 飛ばずに消えた 産まれてすぐに こわれて消えた」という歌詞があります。
実は、この部分は実際にあった悲しい出来事を歌っているという説があるのです。
野口雨情は『しゃぼん玉』を作る15年ほど前に、生まれたばかりの子供を失くしました。
自分の娘と同年代くらいの子供がしゃぼん玉で遊んでいるのをたまたま目にした野口雨情は、
しゃぼん玉と自分の娘のイメージを重ね合わせて、この『しゃぼん玉」を作ったのではないかと考えられています。
そう考えて聞くと、とても悲しい歌に聞こえてきますね。






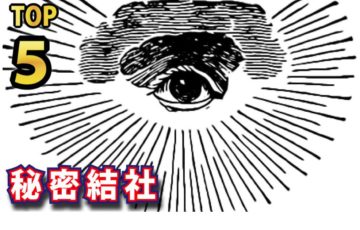
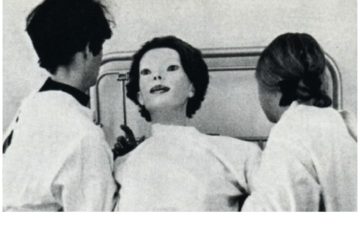


最近のコメント