第5位

第5位はマリのトゥンブクトゥ。いきなりかみそうな地名ですが、54.5℃の記録を残しています。
マリはアフリカの国ですが、そのイメージのまま暑い国なのですね。
そしてそのトゥンブクトゥ、砂漠の民と言われたトゥアレグ族の町なのだそうです。
14世紀にマリ帝国の中心として栄えた町で、西欧では「黄金郷」おうごんきょうと呼ばれていたそうです。
また砂丘に囲まれているので、町全体が砂まみれになることもしばしば。
なんと、冬であっても30℃を越えるのは当たり前なのだそうです。
第4位

第4位は、なんと同着です。1つはリビアのガダミスで、もう一つがチュニジアのケビリです。
両方とも最高気温55℃を記録していますが、実はこの二つの都市、わりと近くにあります。
どちらも砂漠のなかにあるオアシスの町として有名なようです。
まずガダミスですが、人口は7千人。旧市街地は世界遺産に登録されているそうです。
古い建築物は避暑に優れているそうなので、昔から高温地域だったのかもしれないですね。
現代の建物は泥、石灰、木の幹などで造られています。
実はこれも、熱を寄せつけないためのものだそうです。
そしてもう一つの都市、ケビリ。こちらもオアシスの町で、避暑地として知られているようですね。
「オアシス」「避暑地」と言っても55℃の灼熱地獄とは、すごいですよね。
しかし、人類が20万年前から定住しているとの痕跡もあるようです。
理由としては、塩田が近くにあるので、そこへ行くための拠点として人が集っていたことが考えられます。
そんなケビリですが、2001年には「最低気温」が42℃という記録も残したそうです。想像し難いですね。
第2位

先ほどの4位が同着だったのでお次はもう第2位です。
第2位はアメリカのデスバレーで56.7℃。1913年7月10日に記録された気温です。
50℃を超えると、道路で目玉焼きが作れるそうです。
その噂を聞きつけた多くの人が実験して道路が玉子だらけになったため
デスバレー国立公園には「道路で目玉焼きを作る場合はフライパンを使用してください」と書かれているそうです。
もともとこの地域は、地形的に高温が出やすいようですね。
まわりが山脈に囲まれ、夏にはフェーン現象で暖気が流れ込んできます。
しかし盆地のため、その暖気がどこにも逃げられず、留まってしまい高温になってしまうそうです。
それから1929年、1953年には「雨量ゼロ」という記録も出しているそうです。
地球上にもこのような場所があるんですね。
そしてそんなデスバレーも、暑いだけではないのです。実はここ、色んな生き物が集まりやすく、春には砂漠一体が野草で埋めつくされます。
こんな高温地帯なのに…。世の中は、本当にわからないものです。
第1位

栄えある第1位!イラクのバスラで58.8℃。1921年7月8日に記録されました。
ですが、この記録は正式には認められていないものなのです。
長らく世界一暑い場所と認知されてきましたが、近年になって測り間違えではないかという物議も醸しています。
恐らくは観測者の間違いで、本当は53.8℃だったのではないかと言われています。
公式ではないとはいえ、一度は世界一暑いとされていた場所ですから、一応第1位として紹介しておきましょう。
世界一ではない可能性があるにしても最高記録が53℃で平均気温が40℃超えの過酷な環境です。
こういった土地では子供たちは早朝から学校に行き、お昼過ぎには家に帰るように促されているそうです。
また、なるべく陽の当たる場所は避けて、日陰で過ごすよう教育されているそうです。
日本でも、今年のような酷暑の日には、このような対応をするのもいいかもしれません。
日本の最高気温は、高知で41℃。このランキングを見た後だと、低くみえてしまいますが、決してそんなことはありません。
夏の暑さは風物詩なんて甘く見ずに、熱中症対策には念を入れましょうね。




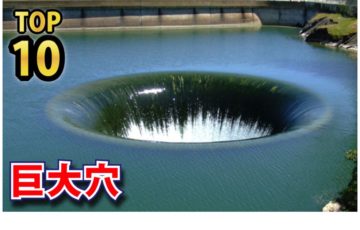


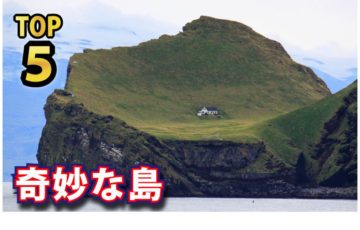
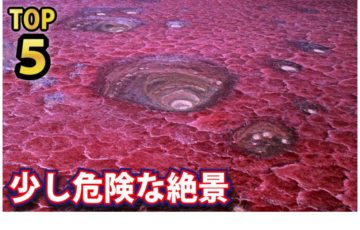



最近のコメント