5、チェリモヤ
チェリモヤは南アメリカのペルーやエクアドルにまたがるアンデス山脈原産の果物です。
リンゴより一回り大きい果物です。皮の部分には粗い凹凸があって、まるで鱗のように見えておいしそうには見えません。

しかし、果肉は白く ねっとりしていてクリームのようで、カスタードアップルともいわれています。
冷やして食べるとより美味しい果物で、その酸味の利いた甘さは、フルーツ入りアイスクリームのようなんです。
ペルーではヨーグルトやアイスクリームを作るのにも使われています。

4、パインベリー
チリ産のイチゴをヨーロッパで品種改良してできたのが、この白いイチゴ、パインベリーです。
普通のイチゴとは違って、大きさは2センチほどしかありません。

パインベリーが市場に出回るようになったのは2010年頃のことで、パインベリーという名前がつけられたのもその頃です。
イチゴなのにパイナップルのような味がすることから、そのように命名されました。
可愛くて美味しいと評判のパインベリーですが、生産農家の規模は小さく、なかなか手に入らない幻の果物です。
春から夏にかけての収穫期でも、なかなかお目にかかることはできません。いつか食べてみたいものです。
3、アキー
アキーの原産地は、カメルーン、アイボリーコースト、ガーナ、トーゴ、シエラレオネといった西アフリカ一帯です。
果実は梨の形をしていて、熟すと鮮やかな赤や黄橙色に変わります。

しかし、この地域では、アキーはほとんど食用にされていません。
普通の果物のような甘みがないばかりか、毒を含んでいるからです。
とりわけ、未熟な状態のアキーは毒がいっぱいで、死亡事故も報告されています。
完熟していても果肉の膜には毒が残っているので、必ず取り除かなくてはなりません。
ところが、この果物は大西洋を挟んだ対岸のジャマイカではとても好んで食べられています。
アキーと魚のタラを炒めた料理はジャマイカの国民食ともいわれるほどポピュラーなのです。
ジャマイカの人たちは、甘くないアキーの特徴を生かし、野菜代わりに食べているのです。
毒のあるものを何でわざわざ食べるのだろう、って思いましたけど、毒のあるものほど食べたくなるんですよね。

2、キワノ
おそらくアフリカが原産地と推定されるキワノは、オーストラリアとニュージーランドで採れるウリ科の果物です。
キワノというのは登録商標で、英語名はホーンド・メロン日本語ではツノニガウリといいます。

キワノを割って中を見ると、緑色の小さな果肉がびっしりと並んでいます。
この果肉はゼリーかブドウのような食感がありますが、それほど甘くはなく、むしろ酸味が優勢です。
そのため、そのままではなくサラダやヨーグルトに入れて食べられています。

マグネシウム、カリウムが豊富に含まれているので高血圧予防や、代謝の改善が期待できます。
オーストラリアやニュージーランド、ヨーロッパ、アメリカ大陸などで栽培されていて、それなりに知られていますが日本では、あまり見かける機会の少ない果物です。
なんだか、見た目が服にくっついちゃうあの植物に似ていると思ったのは私だけでしょうか。
1、ハラ・フルーツ
ハラ・フルーツは、オーストラリア、太平洋諸島、マレーシアが原産の奇妙な形をした果物です。
白い芯の周りにいくつもの楔を放射状に突き刺したような独特な形状をしています。

ハラ・フルーツはほかの果物と同じように生でも食べることができます。
味は薄味のパイナップルといった感じで、格別美味しい果物ではありませんが、
ミクロネシアやモルディブでは非常に一般的で、食用だけでなく様々な用途に使われています。
まずハラ・フルーツの実の繊維はデンタルフロスに使われます。
葉っぱはムシロやバスケットを織るための材料になるだけでなく、料理の香りづけなどのハーブ代わりにも使用されます。
木は干ばつに強く成長も早いため防風林として活用されています。
このように、ハラフルーツは捨てるところなく活用できるため重宝されているようです。





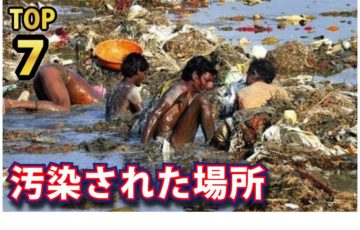






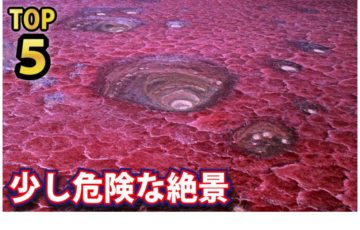
最近のコメント